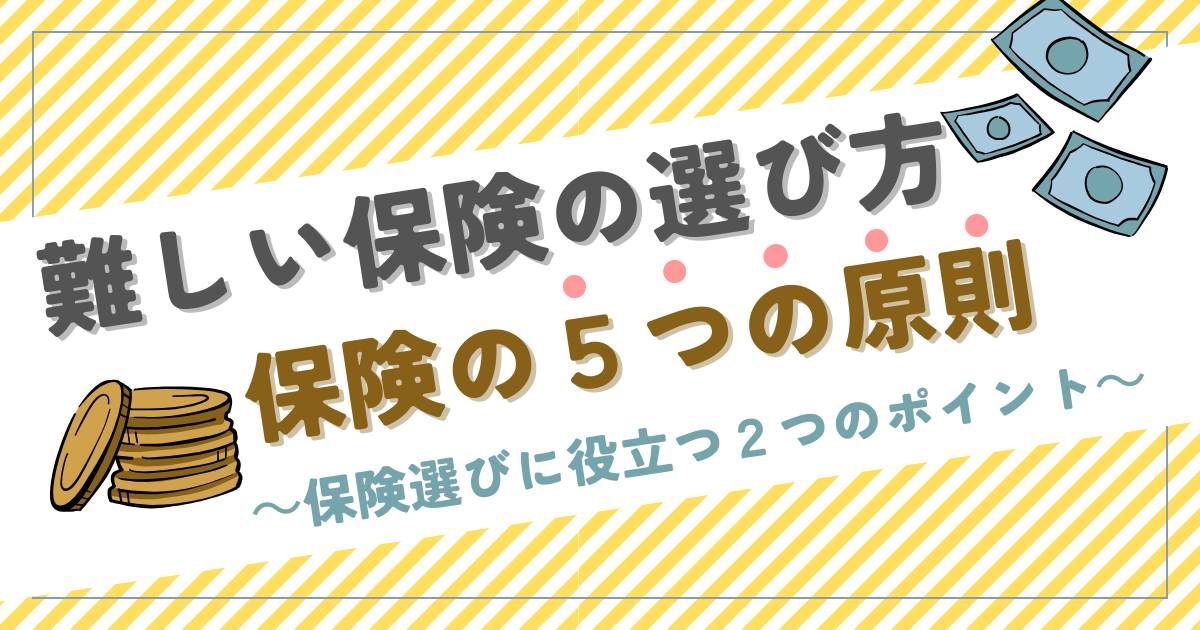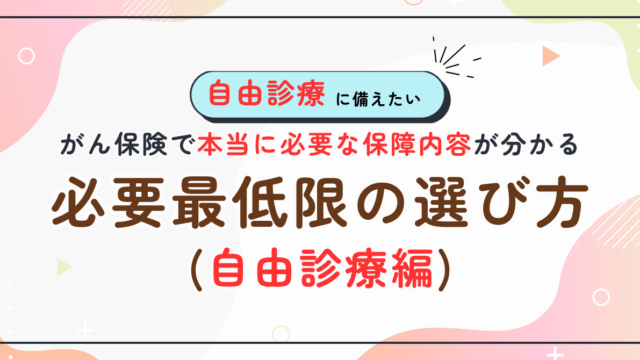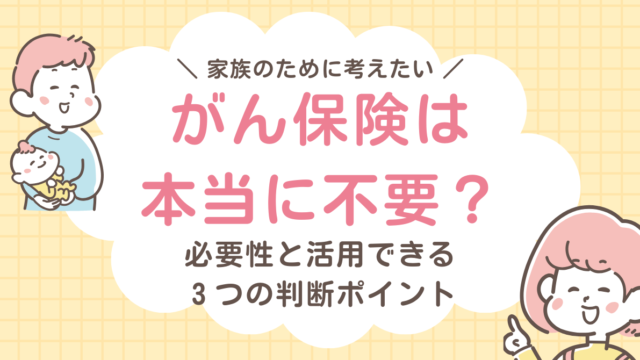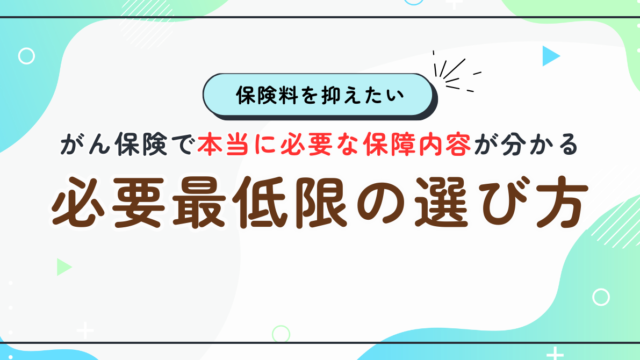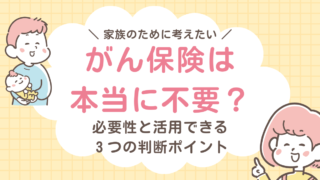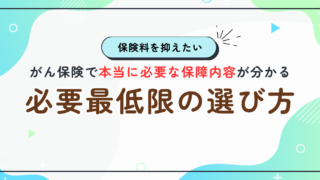- 本当に必要な保険なのか、判断が難しい
- 保険はややこしくて億劫…保険選びのポイントを簡単に知りたい
- いろんな情報であふれていて、ブレずに保険を選ぶのが難しい
家庭を持ち保険の勧誘に遭遇する機会が増えたり、ライフステージが変わり保険を検討中の方が
「できるだけ安くしたいけど、本当に必要な保険は入っておきたい・・・」と判断に困ったり、勧められるままとりあえず入っている方も多いのではないでしょうか。
私は薬剤師とFP3級の資格取得を経て、医療全般に関する基本的な情報収集や解釈、および医療保険などの仕組みなど、一般的かつ客観的な立場での判断や考え方を情報共有させていただけるのではないかと考え、情報発信を始めました。
最近はショッピングモールやイベント会場等での保険の勧誘がピタリと止みました。
この記事では、保険の大事な5つの原則と保険選びの2つのポイントをシンプルにまとめています。
この記事を読めば、難しい保険選びのポイントを簡単に把握でき、生涯にわたり『ご自身で必要な保険を判断し、ブレない選択をする』ための土台を作ることができます。
『保険』の5つの原則
難しい保険選びをシンプルに理解するために、『保険』の5つの原則を見ていきましょう。
- 保険とは相互扶助制度
- 保険の役割は「金銭的な」補償
- 確率低・損失大に備える
- 自ら請求しなければならない
- 損得を求めない:保険=掛け捨て保険と捉える
保険とは相互扶助制度
保険とはどのような制度のことを指すかご存知でしょうか。それは以下のように、
相互扶助=みんなで助け合う制度です。
わが国にはじめて保険制度を本格的に紹介したのは、福沢諭吉『西洋旅案内』(1867年)で 、同書では、「災難請合の事 イシュアランス」として、「人の生涯を請負ふ事」(生命保険や年金)、「火災請合」(火災保険)、「海上請合」(海上保険)など、相互扶助制度としての保険の効用が詳細に示されている
保険の仕組みは、
『幸い何事もなく日常を過ごせている大多数の人たちから集められた保険料を、不幸にも人生が破綻してしまうような大きな損失が出てしまったごくわずかの人を救済するための原資にする』
ことで成り立っています。
保険の役割は「金銭的な」補償
保険の役割は、日々の生活が破綻してしまうような致命的な事象に備えること = 不幸が降りかかってきた時に日常生活を維持するために『金額的に』補償することと言えます。
保険はあくまで金銭的な補償のみであり、起こってしまった不幸を解消してくれるものではありません。
例えば、医療保険は入院費用や通院費用、差額ベッド代の足しにはなるかもしれませんが、その病気が治癒するわけではないですし、
自動車保険は相手への多額の損害賠償の補償の助けになりますが、事故や怪我がなかったことにはなりません。
保険の役割は、あくまで『金銭的』に補償することであり、それ以上の機能はないのです。
確率低・損失大に備える
それでは保険はどのような場面で活用すべきでしょうか。
それは、起こる確率が低いかつ支払わなければならない損失が大きい
事象に備える場合です。
保険の仕組みから裏を返せば、
『起こる確率が高い事象(救済すべき人がたくさん出てきてしまうような事象)に対しては救済に必要な原資が不足する』ために成り立たない、と考えることができ、
『起こる確率が低い事象』に備える保険が保険商品となり得ると言えます。
また、補償すべき損失の大小構わずにあらゆる保険という保険に加入した場合、一つ一つの保険料が少額でも、毎月の支出の中で保険料の比重が重くなってしまい、貯蓄・投資・保険のアンバランスとなってしまいます。
つまり、保険で備えるのは『損失の小さいものでなく支払うことができないほどの額の損失が発生し得る事象』に対してと考えられます。
スマホ保険と対人対物補償(自動車保険)を比べてみましょう。
加入者の約半数で修理等が必要になり、その額も生活防衛費(貯蓄)で対応可能な範囲内と考えられるスマホ保険は、保険で備えるものではないと考えられます。
さらにこのような保険をいくつも加入した場合、不幸な事象が起きてしまった場合の備えとしては万全ですが、近々使う予定のお金の貯蓄、将来掛かってくる教育費や老後資金の準備用の投資が不足する状態になりかねません。
| 確率・損失 | 引用元 | |
|---|---|---|
| スマホを水没した | 45.3% | 東京新聞プレリリース |
| ~20万円前後(買い直し) | J:COM ニュースリリース | |
| 子供が運転する自転車が歩行者を轢いてしまった | 約0.2%程度 | 警察庁 統計表 |
| ~9520万円 | 郡山市市民部セーフコミュニティ課 | |
| 新日本法規 |
以上のことから、保険は確率低・損失大の事象に備えるものとなります。
自ら請求しなければならない
補償してもらうには当然のことながら、基本的にご自身で主体的に請求しなければ補償を受けることができません。
自動車保険のドライブレコーダー連携タイプのものでない限り、保険会社の方から事故等を把握する術がないためです。
『〇〇が起こった時はここに連絡をする』といった風にご自身でどの保険でどの事象に備えているかを認識しておく必要があります。
また、いくつも保険に加入することにより、ある案件が補償対象の場合でも請求し損ねる恐れもあります。こういった管理面からいくつも保険に加入することはあまり好ましくないと考えることができます。
保険は加入した上で、補償を受けるには自ら請求しなければならないという意識を持っておきましょう。
損得を求めない:保険=掛け捨て保険と捉える
ここまでを踏まえると、保険は日々の生活が破綻してしまうような致命的な事象に備えるものであり、その役割から『損得を求めるもの』ではありません。
身近なところで「ちょっとした手術をした時に医療保険に入っていたから手術補償の△円がおりて、これまでの保険料以上に戻ってきたから得をした」というお話を耳にするかもしれません。ですが、偶然得になったのかもしれませんが、保険の本来の役割からは外れてしまっていると考えられます。また、ここまでの保険の原則を押さえていくと自ずと、
保険=『掛け捨て保険』を意味していることが分かるかと思います。
保険選びの2つのポイント
 5つの原則を押さえていただくと、『保険』というものが意外にもスマートに感じられるのではないでしょうか。ここからは種類を問わず保険選びの際のポイントを見ていきましょう。
5つの原則を押さえていただくと、『保険』というものが意外にもスマートに感じられるのではないでしょうか。ここからは種類を問わず保険選びの際のポイントを見ていきましょう。
①感情と数字を区別する
1つ目のポイントは感情と数字を区別することです。
『初めに数字で現状を把握し大きな方向性を決定し、その後に感情を考慮し付加的なアレンジをする』ようにしましょう。
なぜなら、先に感情面(特に漠然とした不安感)が来てしまうと必要以上に保険に加入してしまう場合が多いためです。
例えば自分が死んでしまった時に残された配偶者と子が金銭的に困ることがないよう死亡保険を検討する場合(ここでは毎月の収入の代わりになる収入保障保険)を考えてみましょう。
保険会社から勧められるままに、支払い可能である月5000円の保険に入るのではなく、
- 現在の手取り収入が30万円
- 公的年金である遺族年金が15万円支給される見込み
- その後の支出・生活費も大きく変わらないと想定される
このように数字で状況を把握し、不足分である(30万円-15万円=)15万円の補償額となる月2000円程度に加入するという方向性を決め、そのあとに
- 公的年金が減ってしまう
- 教育費の無償部分がこのまま制度維持されるか不安
といった感情面を考慮し18万円、月2400円の保険に最終決定、という具合です。
あくまで
大きな方向性(必要な補償額や補償範囲)は数字で判断し、その上で
不安がぬぐい切れない等の場合に付加的にアレンジ(補償額を少しだけ上乗せ、ある補償を最小限で追加)するようにしましょう。
もちろん、数字を把握したことで不安などがすっきりした場合にはアレンジの必要がありません。
②公的保険でカバーできない部分を民間保険で補う
上記のように数字で判断するためには、公的保険の補償範囲や補償額の確認は必須となります。そして、公的保険のみでは不足する分を民間保険で補うようにしましょう。
病気やケガのリスクに対する高額療養費制度や傷病手当金、障害リスクに対する障害年金、介護リスクに対する介護保険など、さまざまなケースに対して既に公的保険が備わっています。
公的保険でカバーできない部分を民間の保険で補うようにしましょう。
まとめ
保険の5つの原則と保険選びの2つのポイントについて見てきました。
5つの原則は以下の通りです。
- 保険とは相互扶助制度
- 保険の役割は「金銭的な」補償
- 確率低・損失大に備える
- 自ら請求しなければならない
- 損得を求めない:保険=掛け捨て保険と捉える
保険選びの際には、2つのポイントをベースにアプローチしましょう。
- 感情と数字を区別する
- 公的保険でカバーできない部分を民間保険で補う
5つの原則と2つのポイントを一つの基準としてご理解いただくことで、ご自身で必要な保険を判断し、ブレない選択をすることができます。
保険で備えるべきリスクを特定し確実に備えつつ、貯蓄、投資に資金を割り振ることができれば、より安心して日々の生活を送ることができます。

また長期的な視点から、保険はライフステージによって最適解が変わるため、見直しに迫られる時が必ずやってきます。
『生涯にわたりご自身で判断するための土台』として本記事の内容を活かしていただければ幸いです。
さらに、それを身近にいる大切な人にもご自身の言葉で伝えることができれば、大切な人も、保険で悩んだり必要以上の保険の支払いで生活が圧迫されるようなことがなくなります。
これからも皆さんの日々の生活が『より良く』なるような情報を発信していきます。
以上、ぐぅでした。
※本記事の画像はAI生成(Canva利用)です。